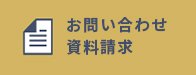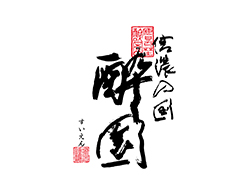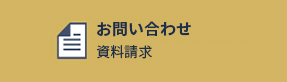中国への
販路開拓について
今、なぜ中国なのか
中国市場の魅力〜日本食品の輸出機会
2020年末時点での中国市場は、14億1,200万人という巨大な人口を誇り、日本食品の輸出市場として非常に魅力的です。この市場には多くの要素が魅力を加えています。
まず、経済的な観点から見ると、中国は一人当たりGDPが高水準で、一人当たりの可処分所得も増加しています。これにより、中国の消費者は高品質な食品への需要が高まっており、特に食品・タバコ・酒類の消費が増加しています。さらに、フードデリバリー市場も急成長し、日本食品のデリバリー需要が拡大しています。
2022年3月にJETROが発表した「海外有望市場商流調査(中国)」によれば、中国市場では、日本食品に対するイメージも非常に良好です。中国の消費者は、日本食品を高品質で健康的で、味も繊細なものと認識し、高品質なライフスタイルを追求する層から支持を受けています。また、訪日経験者や日本文化愛好者も市場を形成しており、需要が高まっています。
さらに、訪日中国人の増加も市場にプラスの影響を与えています。中国からの観光客数が急増し、日本での「爆買い」も存在します。訪日中国人は日本食品に対する受容度が高く、中国市場における日本食品の人気を高めています。
しかし、風評被害が存在し、処理水問題が日本食品に対する不安を引き起こしています。市場の多様性も特徴で、大都市では外国料理に対する受容度が高い一方、内陸都市では地元の食文化が主流です。これにより、異なる市場ニーズに対応する機会が広がっています。
最後に、販売チャネルも重要な要素です。日系スーパーマーケットや高級スーパーは、日本食品の販売において重要な役割を果たしており、市場を拡大しています。
総括すると、中国市場は日本食品の輸出にとって大きな機会を提供しており、高品質な食品への需要が高まっています。しかし、風評被害や処理水問題に対処する必要があります。成功を収めるためには、市場ニーズに合わせた戦略を展開し、品質とブランド価値を重視することが不可欠です。
中国における巨大EC市場とその成功要因
中国は、日本では想像できないほどインターネットが普及しています。
店舗での買物、交通機関の利用、あらゆる場面でスマホ決済が当たり前になっており、財布を持たずに外出する人が多くなっています。
EC市場においても、2021年の独身の日(11月11日)に関連するEC販売額は、最大手「天猫」が9兆3094億円、2番手「京東」が6兆150億円と、過去最高を更新。
日本のEC最大手「楽天」の2021年販売額が1兆34億円であることからも中国の巨大なEC市場がうかがえます。
中国人が物品を購入するときのルーティンとして、その商品が本物かどうか、どんな特徴があるかなどを必ずインターネットで検索して真贋確認を行うこと、その際は企業の公式ホームページよりも掲載審査の厳しいSNSを信用することが挙げられています。
EC市場での成功要因は「認知度向上」で、知名度のない新規商品をいきなり大成功に導くことは困難ですが、展開商品にふさわしいSNSやECサイトで情報発信を重ねることで販路開拓は可能になります。
また、KOL(Key Opinion Leader)やKOC(Key Opinion Consumer)と呼ばれるインフルエンサーを効果的に活用し、「認知度向上」に繋げていく戦術も重要になります。
現地コーディネーター

現地コーディネーター深水エリナ
(株)ERINATRADING JAPAN 代表取締役
惠莉奈(上海)易有限公司 董事長総経理
アパマンショップホールディングスの経営企画・広報を経て、2008年に上海へ。
株式会社インフォブリッジマーケティング&プロモーションにて、中国のマーケティングリサーチおよびセールスマネジャーとして従事。
2013年、アイザックグループに参画し、日系企業のマーケティングリサーチ、データ分析、システム開発サービスなどを展開。
2017年、訪日インバウンドおよび中国でのSNSプロモーション事業を展開する上海勒訊企業管理諮詢有限公司(SMART)に参画。
2019年、SMARTの在日本の窓口として(株)スマートビジネスコンサルティング(SBC)を設立。
2021年12月、惠莉奈(上海)貿易有限公司を設立し、食器ブランドNoritakeの中国地区総代理店としてテーブルウエア商品の販売を行うとともに、中国でマーケティングリサーチ、プロモーション、ECやオフラインでの商品の販売、販売ルート開拓など幅広く手掛けている。
2022年、SBCを(株)エリナトレーディングに改称し、日本酒、焼酎、泡盛や加工食品はじめ、江戸切子、薩摩切子、包丁などのテーブルウエア、キッチンウエアを中心に中国に新規販売展開させる事業を行っている。

現地コーディネーター浮田真吾
(株)ERINATRADING JAPAN 九州OFFICE
所長 (利酒師、焼酎利酒師)
日本通運(1984-91)、北九州市(1991-2010)、上海東和旅行社(2010-)での経験を通じて国際物流、地方行政、インバウンド、中国経済・中国マーケットに詳しく、現在は(株)ERINATRADING JAPAN 日本側開発担当として中国展開希望企業開拓を行っている。
<主な実績>
日通時代に、輸入生鮮貨物、アジア太平洋博覧会(1989年)国際パビリオン、佐賀熱気球大会国際輸送担当。北九州市職員時に、国際見本市主催(6本)、物流政策・企業誘致、初代上海事務所長として、路線誘致、クルーズ誘致、インバウンドプロモーション、国際部課長として習近平中国国家副主席の北九州市視察(2009年)の総合ロジなどを担当。上海東和旅行社総経理として、社員旅行、インセンティブツアー、高校生修学旅行、小中学生サッカーキャンプなど特色のある訪日旅行を多数実施。2020年、コロナ禍のため帰国後、リモートで旅行業を行うとともに、(株)ERINATRADING JAPANと共同で北九州市の中国向けSNS情報発信業務を実施。2021年よりERINATRADING JAPANの九州Office所長。日本酒、焼酎、泡盛の酒蔵や酒造組合、江戸切子、薩摩切子、関の包丁はじめテーブルウエア関連企業商品の中国向販売展開企業を多数開拓。
中国で好まれる日本食

和食
中国国内の日本食レストランや訪日旅行を通じて、日本食ファンになる中国人は多数います。
一般的に中国人が好む日本食といえば、
- 刺身
- 寿司
- 天ぷら
- 焼肉
- すき焼き
- しゃぶしゃぶ
- 和牛(ステーキ)
- うなぎ
などであり、訪日旅行の際には本場の和食を一度は食べたいと言われる方が多数です。
B級グルメ
- ラーメン
- うどん
- お好み焼
- たこ焼き
など、いわゆるB級グルメも人気です。
日式料理
北京や上海などの大都市では、日本人オーナー・日本人料理人による日本食レストランもありますが、大都市あるいは地方都市の多くは中国人オーナー・中国人料理人による「日式料理店」が大多数であり、コロナ禍においてはその傾向はさらに強くなっています。
「日式料理店」で提供される料理は、中国人の思考で中国人向けにアレンジされた味付けやメニューも多く、日本人から見るととても日本料理とは言えないものもあります。
これは日本において日本人好みに変化した中華料理、イタリア料理、フランス料理などにも言えることです。
「日式料理」であっても、使われる食材は日本のものが求められており、ロックダウンを通じて盛んになった「おうち料理」における「日式料理」あるいは「日本料理」にも日本の食材が求められています。
特にロックダウン後は、友人や知人、団体購入を通じて親密になったご近所さんを招いたホームパーティが増えることも予想されており、日本から直輸入された食材や商品はさらにもてはやされることが考えられます。
訪日旅行時に味わった料理を家庭で再現しふるまうスタイルが今後も増えてくるでしょう。
中国における販路拡大実績
2018年~現在
日系大手高級食器ブランド、販路開拓支援から総代理店化し現地に根付いた販路開拓
2018年より、中国現地販社のECおよび販路拡大のコンサルティングおよびオペーレーションを開始。
2年で事業の黒字化を達成したものの、継続的に事業拡大できる人材が中国におらず、2020年1月に中国の総代理店として事業を開始。
年間売上は5億円以上。
ミシュランレストラン、高級会所(中国版料亭)、百貨店、食品卸会社等、取引店舗は高級路線を中心に500店舗以上にのぼる。
2021年~現在
中国販売展開サポート業務
中国販売展開を希望している日本全国の酒蔵(日本酒、焼酎など)や関の包丁、江戸切子などの販路開拓を行っている。